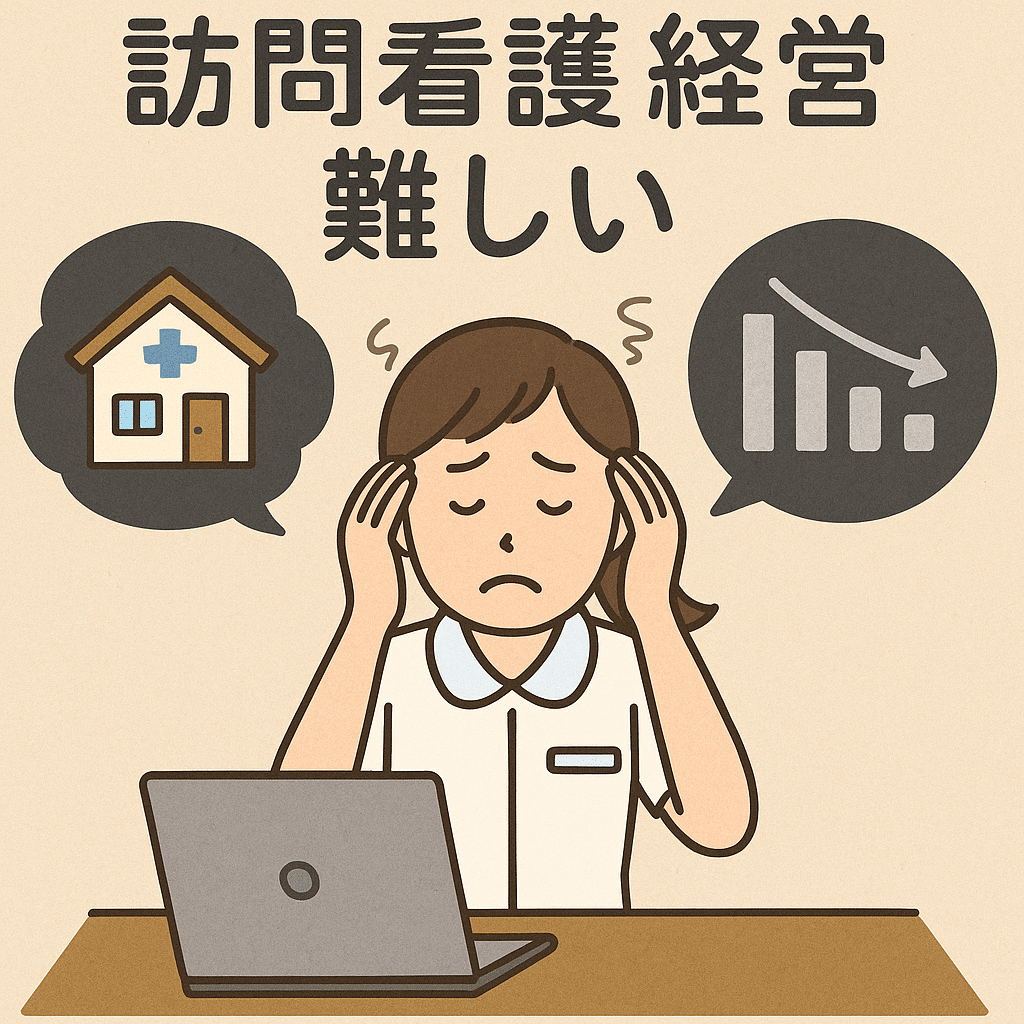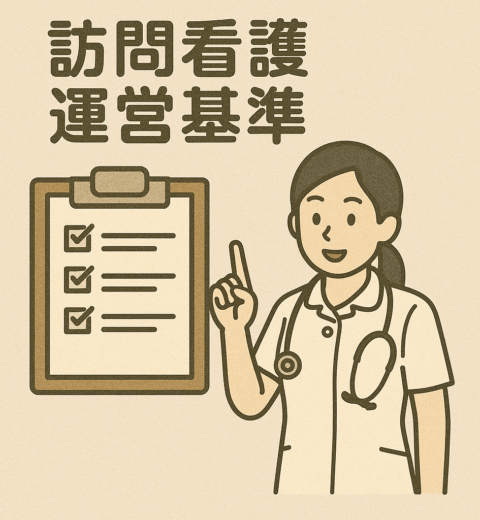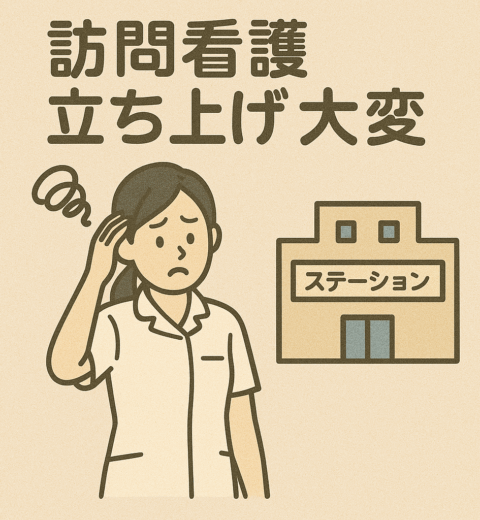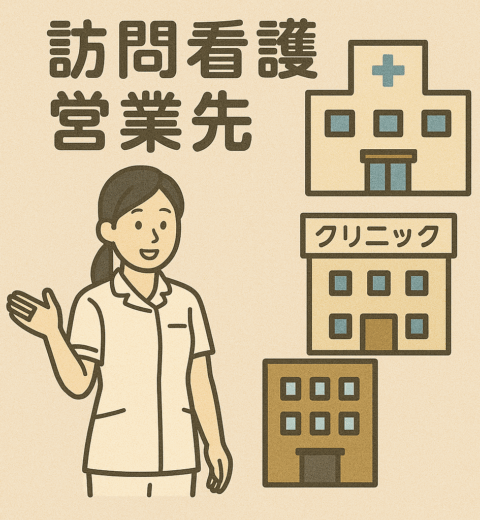長年の看護師経験の中で、「自分ならもっと質の高いケアを提供できるのに」「もっとスタッフが働きやすい環境を作れるはずだ」と感じたことはありませんか。
その想いを実現するために、「訪問看護ステーションでの独立」という選択肢が、ふと頭をよぎる方も少なくないでしょう。
しかし、いざ独立となると、経営のことは全くの未知の世界です。
「訪問看護の経営は難しい」という声も聞こえてきて、期待と同時に大きな不安に襲われ、なかなか一歩を踏み出せないかもしれません。
この記事では、なぜ訪問看護の経営が「難しい」と言われるのか、その具体的な理由をデータと共に徹底解説します。
さらに、その壁を乗り越え、あなたの理想とする看護を実現するための成功の条件まで、明確な道筋を示します。
漠然とした不安を具体的な知識に変え、独立への第一歩を踏み出すための羅針盤として、ぜひ最後までお読みください。
なぜ訪問看護の経営は「難しい」のか?データで紐解く6つの理由
訪問看護ステーションの経営が「難しい」と言われる背景には、単なるイメージではなく、構造的な課題が存在します。
ここでは、その理由を6つの側面に分け、具体的なデータも交えながら詳しく解説していきます。
これらの課題を正しく理解することが、成功する経営への第一歩となります。
理由1:慢性的な人材不足と激化する採用競争
訪問看護事業の根幹を支えるのは、看護師をはじめとする専門職スタッフです。
しかし、この「人材の確保」が、経営における最大の壁として立ちはだかります。
高齢化で訪問看護のニーズが高まる一方、労働人口は減少しており、看護師の獲得競争は激化の一途をたどっています。
実際に、2025年9月時点での看護師の有効求人倍率は3.5倍を超えており、これは求職者1人に対して3.5件以上の求人があるという「超売り手市場」を意味します[^1]。
また、病院勤務と比べて、訪問看護は一人で利用者の自宅へ赴き、多様な状況に臨機応変に対応する必要があるため、精神的・肉体的な負担が大きいと感じる看護師も少なくありません。
こうした要因が重なり、多くのステーションが慢性的な人材不足に悩み、人員配置基準を満たすことすら困難になるケースがあるのです。
| 人材確保が難しい要因具体的な内容高い有効求人倍率看護師は超売り手市場であり、医療機関や他の介護事業者との採用競争が激しい。業務負担の大きさ病院勤務と異なり、単独での判断や緊急対応が求められ、精神的・肉体的負担が大きい。地域による偏在特に地方や過疎地域では、看護師の確保が都市部以上に困難な傾向がある。 |
|---|
理由2:資金・ノウハウ不足という経営資源の壁
多くの訪問看護ステーションは中小規模で運営されており、資金や経営ノウハウといった経営資源に限りがあります。
特に、臨床経験は豊富でも経営は未経験という方が独立する場合、この壁はより一層高くなります。
事業を始めるには、事務所の賃料や車両の購入費、備品代などの初期投資に加え、事業が軌道に乗るまでの数ヶ月分の人件費や運営費といった運転資金が必要です。
これらの資金調達がまず最初のハードルとなります。
さらに、経営が始まれば、利用者を獲得するためのマーケティングや営業活動、スタッフの労務管理、煩雑な請求業務など、看護業務とは全く異なる知識やスキルが求められます。
経営ノウハウの不足から適切な戦略を立てられず、ICT導入や研修制度の整備といった未来への投資もままならない、という状況に陥りがちです。
理由3:事業計画を揺るがす法規制・制度改正への対応
訪問看護事業は、介護保険法や医療保険法といった国の制度の上で成り立っています。
そのため、数年ごとに行われる介護報酬や診療報酬の改定が、ステーションの収益に直接的な影響を及ぼします。
例えば、2024年度の介護報酬改定では、訪問看護の基本報酬が平均で0.5%引き上げられた一方で、特定の加算要件が厳格化されるなど、経営にとってはプラスとマイナスの両側面がありました[^5]。
| 近年の主な法規制・制度改正経営への影響介護報酬・診療報酬改定基本報酬や加算の変更により、ステーションの収益が大きく変動する可能性がある。BCP(事業継続計画)策定の義務化2024年4月から義務化。災害や感染症発生時にも事業を継続するための計画策定が必須。ハラスメント対策の義務化2025年4月から義務化。利用者やその家族からのハラスメント対策が求められる。 |
|---|
このように、制度は常に変化しており、その情報をいち早くキャッチし、適切に対応し続けなければなりません。
情報収集や解釈、対応策の策定に時間と労力がかかり、経営の不安定要因となり得るのです。
理由4:利用者獲得の生命線となる地域連携の構築
訪問看護ステーションは、地域包括ケアシステムの中で機能する一つのパーツです。
単独で存在するのではなく、地域の病院、クリニック、居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)、行政などと連携して初めて、質の高いサービスを提供できます。
この地域連携は、利用者を安定的に獲得する上での生命線とも言えます。
特に、病院の退院調整看護師や地域のケアマネージャーとの信頼関係は極めて重要です。
彼らから「あのステーションなら安心して患者さんや利用者さんを任せられる」と思ってもらえなければ、新規の依頼はなかなか舞い込んできません。
連携が不足すると、情報共有が滞りサービスの質が低下するだけでなく、地域での評判も上がらず、利用者獲得に苦戦するという悪循環に陥ってしまいます。
地道な挨拶回りや定期的な情報交換、合同カンファレンスへの参加など、継続的な関係構築の努力が不可欠です[^4] [^7]。
理由5:保険制度に依存する不安定な収益構造
訪問看護ステーションの収入の大部分は、介護保険や医療保険からの報酬です。
この収益構造は、国の制度に守られている反面、本質的な不安定さを内包しています。
なぜなら、報酬は提供したサービスの量、つまり訪問件数に大きく左右されるからです。
例えば、利用者の体調が悪化して入院したり、残念ながらお亡くなりになったりすると、その方の分の訪問は無くなり、売上は直接的に減少します。
また、近年は競合となるステーションが増加しており、限られたパイ(利用者)を奪い合う構図が生まれています。
質の高いケアを提供していても、利用者の状態変化という外部要因や、激化する競争によって収益が安定しにくい。
これが、訪問看護経営の難しさの一つです。
理由6:スタッフの心身を疲弊させる過酷な労働環境
訪問看護の現場は、病院とは異なる厳しさがあります。
利用者の自宅から自宅へと車や自転車で移動するため移動時間が長く、身体的な負担は少なくありません。
また、24時間対応体制をとるステーションでは、オンコール(緊急時対応の待機)による精神的なプレッシャーも伴います。
さらに、利用者の自宅は必ずしも衛生的な環境とは限らず、感染症のリスクにも常に晒されています[^9]。
こうした厳しい労働環境は、スタッフの疲弊や燃え尽きにつながりやすく、高い離職率の一因となっています。
そして、スタッフが辞めてしまうと、残されたスタッフの負担はさらに増え、結果として理由1で述べた「人材不足」に拍車をかけるという悪循環に陥ってしまうのです。
【リアルな数字】訪問看護の収益性と経営者の年収は?
「経営は難しい」という現実の一方で、やはり気になるのは「実際、儲かるのか?」「経営者になったら年収はいくらくらいになるのか?」というお金の話でしょう。
理想の看護を追求するためにも、事業の継続性と経済的な安定は不可欠です。
ここでは、訪問看護ステーションの収益構造と経営者の年収について、リアルな数字を交えながら解説します。
訪問看護ステーションは儲かる?黒字・赤字の現実と採算ライン
訪問看護事業の収益性を判断するには、まず収支構造を理解する必要があります。
売上の大部分は介護保険・医療保険からの報酬であり、支出の半分以上を人件費が占めるのが一般的です。
訪問看護ステーションの収支モデル(一例)
| 項目金額(月間)備考売上400万円看護師5名体制、月間400回の訪問を想定支出350万円 ├ 人件費240万円給与、賞与、社会保険料など(売上の60%)├ 事務所家賃20万円 ├ 車両関連費15万円リース代、ガソリン代、保険料など├ 通信費・水道光熱費10万円 ├ 消耗品費10万円衛生用品、事務用品など├ 採用・広告費15万円 └ その他経費30万円リース料、雑費など営業利益50万円売上 – 支出 |
|---|
上記のモデルはあくまで一例ですが、黒字化するための採算ライン(損益分岐点)は、常勤看護師1人あたり月間80〜90回程度の訪問が一つの目安とされています。
つまり、看護師5名体制であれば、月間400〜450回の訪問件数を安定的に確保できなければ、経営は赤字に陥るリスクがあります。
「儲かる」という状態は、この採算ラインを大きく上回り、安定的に利益を出し続けられることを意味します。
経営者の平均年収と収入を上げるためのポイント
経営者の年収は、ステーションの利益から支払われる役員報酬によって決まります。
そのため、事業規模や利益率によって大きく変動しますが、一般的には400万円〜1,000万円以上と幅があります。
事業規模別の経営者年収(目安)
| ステーションの規模(スタッフ数)営業利益(年間)経営者の年収(目安)小規模(〜5名)300万円〜600万円300万円〜500万円中規模(6名〜10名)600万円〜1,200万円500万円〜800万円大規模(11名〜)1,200万円〜800万円〜 |
|---|
経営者として収入を上げるには、ステーションの利益を増やす必要があります。
具体的には、以下のような施策が考えられます。
- 加算の積極的な取得:24時間対応体制加算やターミナルケア加算など、単価の高い加算を算定できる体制を整える。
- 医療保険利用者の割合を増やす:介護保険に比べて医療保険の方が報酬単価が高い傾向にあるため、医療依存度の高い利用者を積極的に受け入れる。
- 自費サービスの提供:保険適用外の個別サービス(長時間の見守り、旅行の付き添いなど)を提供し、新たな収益源を確保する。
- 徹底したコスト管理と業務効率化:ICTツール導入などで無駄な経費を削減し、利益率を高める。
廃業率はどのくらい?失敗するステーションに共通する原因
訪問看護ステーションの廃業率は、決して低い数字ではありません。
正確な統計は難しいものの、開設から3年以内に約3割、5年以内に約5割が廃業に追い込まれるとも言われています。
失敗し、廃業に至るステーションには、これまで解説してきた「経営が難しい理由」を乗り越えられなかったという共通点があります。
| 失敗するステーションに共通する主な原因計画性の欠如:甘い収支計画で見切り発車し、早々に資金がショートする。人材の離反:劣悪な労働環境によりスタッフが定着せず、人員基準を割ってしまう。利用者獲得の失敗:地域連携を軽視し、営業活動を怠った結果、利用者が集まらない。制度への無理解:報酬改定に対応できず、請求漏れや返戻が多発し、資金繰りが悪化する。 |
|---|
これらの原因は単独で発生するのではなく、相互に関連し合って経営を圧迫します。
失敗のリスクを正しく認識し、事前に対策を講じることが何よりも重要です。
難しいからこそ差がつく!訪問看護経営を成功に導く5つの鉄則
訪問看護の経営が多くの課題を抱えていることは事実です。
しかし、その「難しさ」を乗り越えた先には、大きなやりがいと、理想の看護を実現できる未来が待っています。
ここでは、困難な状況だからこそ競合との差がつく、経営を成功に導くための5つの鉄則を具体的に解説します。
鉄則1:「理念」と「数字」を両立させる事業計画と資金計画
成功する経営の土台となるのが、情熱(理念)と冷静な分析(数字)に基づいた事業計画です。
あなたが「どんなケアを実現したいのか」「どんなステーションを作りたいのか」という理念を明確に言語化しましょう。
その理念が、スタッフを惹きつけ、地域の連携先から信頼を得るための核となります。
しかし、理念だけでは事業は継続できません。その理念を実現するために、どれくらいの売上が必要で、経費はどれくらいかかるのかを具体的に数値化した収支計画が不可欠です。
| 事業計画書に盛り込むべき主要項目経営理念・ビジョン:ステーションが目指す姿、地域への貢献など。サービス内容:提供する看護サービスの特徴、専門性、対応エリアなど。市場分析:商圏の人口動態、競合ステーションの状況、地域の医療ニーズなど。マーケティング戦略:利用者獲得のための具体的な営業計画。人員計画:スタッフの採用・育成計画。収支計画:3〜5年間の売上、経費、利益の見通し。資金計画:必要な初期投資と運転資金、その調達方法。 |
|---|
資金計画においては、自己資金だけでなく、公的な融資制度や補助金・助成金の活用も積極的に検討しましょう。
| 主な資金調達方法特徴日本政策金融公庫 新創業融資制度無担保・無保証人で利用できる場合があり、創業者にとって利用しやすい。地方銀行・信用金庫の創業融資地域の情報に精通しており、親身な相談が期待できる。各種補助金・助成金IT導入補助金やキャリアアップ助成金など、返済不要の資金。国や自治体の制度を要確認。 |
|---|
鉄則2:「ここで働きたい」と思わせる人材戦略と職場環境づくり
最大の経営課題である人材不足を克服するには、「選ばれるステーション」になるしかありません。
そのためには、スタッフが「ここで長く働きたい」と心から思えるような魅力的な職場環境を創り出すことが重要です。
給与や休日などの待遇改善はもちろんのこと、キャリアアップの支援や働きがいを感じられる仕組みづくりが求められます。
| 魅力的な職場環境を構成する要素具体的な取り組み例公正な待遇近隣の医療機関や競合ステーションを調査し、地域水準以上の給与を設定する。明確な評価制度と昇給制度を設ける。働きやすい勤務体系年間休日125日以上、短時間正社員制度、フレックスタイム制、子の看護休暇などを導入する。キャリア支援と教育認定看護師などの資格取得支援制度を設ける。定期的な社内研修や勉強会を実施する。良好な人間関係経営者がスタッフと定期的に面談し、意見交換の場を設ける。感謝を伝え合う文化を醸成する。業務負担の軽減ICTツールを導入し、記録や情報共有の時間を削減する。オンコール負担を軽減する仕組みを工夫する。 |
|---|
鉄則3:地域のキーパーソンを味方につける戦略的「営業」と「連携」
利用者獲得は、待っているだけでは始まりません。
地域の医療・介護関係者、特にキーパーソンとなる人たちに自社のステーションを知ってもらい、信頼関係を築くための戦略的な活動が不可欠です。
これは単なる「営業」ではなく、共に地域医療を支えるパートナーとしての「連携」を構築するプロセスです。
誰に、何を、どのように伝えるべきか、計画的にアプローチしましょう。
| 主な連携先アプローチ方法・伝えるべき内容居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)定期的に訪問し、ステーションの空き状況や対応可能な症例などを情報提供する。自社の強み(24時間対応、リハビリ専門職在籍など)を明確に伝える。病院・クリニック(退院調整看護師、医師)退院前カンファレンスに積極的に参加し、顔の見える関係を築く。医療依存度の高い患者の受け入れ実績をアピールする。地域包括支援センター担当エリアの高齢者の特性やニーズについて情報交換を行う。センター主催のイベントなどに協力する。 |
|---|
鉄則4:ICT活用で業務効率化とケアの質を両立させる
限られた人材で質の高いサービスを提供し続けるためには、業務の効率化が必須です。
ここで大きな力を発揮するのが、ICT(情報通信技術)の活用です[^9]。
日々の記録やスタッフ間の情報共有、訪問スケジュールの管理などを効率化することで、看護師が本来のケア業務に集中できる時間を創出します。
| ICTツールの種類導入によるメリット電子カルテ・記録アプリ訪問先でスマホやタブレットから記録が可能に。記録時間を平均40%削減。ステーションに戻ってからの残業を減らす。ビジネスチャットツールスタッフ間のリアルタイムな情報共有を促進。電話連絡の手間を削減し、迅速な対応を可能にする。訪問ルート最適化システム複数の訪問先を効率的に回るルートを自動で作成。移動時間を平均25%削減し、訪問件数を増やす。勤怠管理・シフト作成システム煩雑なシフト作成や給与計算の業務負担を大幅に軽減する。 |
|---|
ICTの導入には初期費用がかかりますが、IT導入補助金などを活用することで負担を軽減できます。
長期的に見れば、生産性の向上やスタッフの負担軽減、離職率低下に繋がり、経営の安定に大きく貢献します。
【独自ノウハウ】競合調査と利用者獲得を加速させる「みつける訪看ex」活用術
経営を成功させるには、開業エリアの市場を理解し、自社の強みを効果的にアピールすることが重要です。
ここで強力なツールとなるのが、全国1,500件以上の訪問看護ステーション情報を網羅したポータルサイト「みつける訪看ex」です。
このセクションでは、競合記事にはない独自のノウハウとして、具体的な活用術をご紹介します。
ステップ1:開業前の徹底した競合分析
開業エリアを決めたら、まずは「みつける訪看ex」でその地域の競合ステーションを徹底的に調査しましょう。
- 検索機能の活用:「地域」で絞り込んだ後、「24時間対応」「精神科訪問」「小児対応」といった対応サービスや、「理学療法士」「認定看護師」といった在籍資格者で検索します。
- 分析のポイント:これにより、「このエリアにはリハビリに強いステーションが多い」「夜間対応できる事業所が少ない」といった市場の特性が見えてきます。競合が手薄なサービス領域こそ、あなたのステーションが差別化を図るべきポイントです。
ステップ2:開業後の戦略的な情報発信
自社のステーションを開設したら、今度は「みつける訪看ex」を情報発信の場として活用します。
- 強みを明確に:ステップ1の分析で見出した自社の強み(例:夜間対応可能、ALS経験豊富な看護師在籍など)を、実績タグや紹介文で明確にアピールします。
- ケアマネージャーの視点を意識:「みつける訪看ex」の利用者の多くは、利用者を探しているケアマネージャーや病院の退院調整看護師です。彼らがステーションを探す際に「何を重視するか」を意識し、「24時間対応バッジ」や「PT/OT/ST在籍情報」などを分かりやすく表示することで、問い合わせに繋がりやすくなります。
このように「みつける訪看ex」を戦略的に活用することで、データに基づいた事業戦略の立案と、効率的な利用者獲得の両方を実現できるのです。
独立を決意したら。成功に向けた具体的な準備ロードマップ
訪問看護ステーションの経営は、思いつきで始められるものではありません。
独立を決意してから実際に事業を開始するまでには、入念な準備と計画的な手続きが必要です。
最後に、成功への道を一歩ずつ着実に進むための具体的なロードマップを提示します。
| フェーズ主なタスク期間の目安構想・情報収集フェーズ経営理念の明確化、セミナー・講習会への参加、経営者仲間との交流、市場調査(みつける訪看ex活用)6ヶ月〜1年計画策定フェーズ事業計画書・収支計画書の作成、資金計画の策定、融資・補助金に関する相談3ヶ月〜6ヶ月設立・申請フェーズ法人設立(株式会社、NPO法人など)、事務所・車両の確保、資金調達の実行、都道府県への指定申請3ヶ月〜6ヶ月開業準備フェーズ人材の採用・教育、備品(医療機器、衛生用品など)の準備、営業活動の開始(地域連携先への挨拶回り)2ヶ月〜3ヶ月開業ステーション運営開始- |
|---|
このロードマップはあくまで目安です。
各ステップを着実にクリアしていくことが、順調なスタートダッシュと、その後の安定経営に繋がります。
一人で抱え込まず、必要に応じてコンサルタントや行政書士などの専門家の力も借りながら、準備を進めていきましょう。
まとめ:訪問看護の経営は「難しい」が、あなたの理想のケアを実現する道でもある
この記事では、訪問看護ステーションの経営が「難しい」と言われる6つの具体的な理由から、収益性のリアルな数字、そして成功への鉄則までを詳しく解説してきました。
人材不足、資金繰り、制度改正への対応など、乗り越えるべき壁は確かに少なくありません。
しかし、これらの課題は、裏を返せば、しっかりとした準備と戦略があれば乗り越えられるということです。
何よりも大切なのは、あなたが長年の臨床経験で培ってきた「もっと良いケアを提供したい」という熱い想いです。
その理念を事業計画という設計図に落とし込み、人材育成や地域連携といった一つひとつの課題に真摯に取り組むことで、道は必ず開けます。
訪問看護の経営は、単にお金を稼ぐためのビジネスではありません。
それは、あなたが理想とする看護を自らの手で形にし、地域社会に貢献するための、挑戦しがいのある道なのです。
この記事が、あなたの漠然とした不安を確かな一歩に変えるきっかけとなれば幸いです。
起業にあたって避けるべき失敗事例とその回避策は何ですか?
代表的な失敗事例は、資金計画の甘さから運転資金の枯渇、労務管理のずさんさによるスタッフの離職、マーケティング不足による利用者獲得の失敗です。これらを避けるためには、保守的な資金繰り計画を行い、労働法規の遵守とスタッフとの良好なコミュニケーションを確保し、徹底した市場調査と差別化戦略を立てることが必要です。
訪問看護起業において成功者が意識している重要なポイントは何ですか?
成功する起業者は、事業計画書の作成に重きを置き、資金計画を十分に行い、適切な経営戦略と差別化を図ることに努めています。また、スタッフの採用と育成、行政手続きの正確な実施、地域医療との連携を重視し、失敗事例から学びながら計画的に進めることが重要です。
訪問看護ステーションを開業する際の具体的なステップは何ですか?
開業のための基本的なステップは、理念を固めて事業計画書を作成すること、法人設立を行うこと、必要な設備と人員を準備すること、行政の指定申請を行うこと、地域の医療・介護関係者との連携と営業を進めること、行政の利用者受入れ認定を取得し、その後の地域連携と営業活動を行うことです。
訪問看護の起業にはどれくらいの資金が必要ですか?
一般的に、訪問看護ステーションの立ち上げには約500万円から1,500万円の資金が必要です。この金額には、法人設立費用、事務所契約費用、設備・備品購入費、車両購入やリース費、広告宣伝費、最低6ヶ月分の運転資金が含まれます。
訪問看護での起業の市場の将来性はどのように評価されていますか?
訪問看護の需要は高齢化と在宅医療推進により今後も拡大し続けると予測されており、2040年までに高齢者人口や利用者数が増加する見込みです。これは、適切な経営を行えば安定した事業基盤を築くことが可能だと示しています。